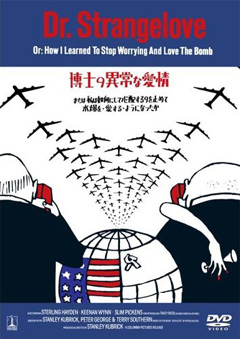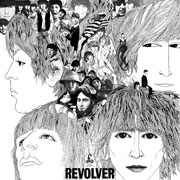「シンデレラマン」(2005) [映画の観方]
<原題>Cinderella Man
<監督>ロン・ハワード
<出演>ラッセル・クロウ、レネー・ゼルウィガー、ポール・ジアマッティ
-------------------------------------------------------------------------
■ハリウッド的
ラッセル・クロウ主演、共演にレネー・ゼルウィガー、
監督は「アポロ13」のロン・ハワードと聞けば、
だいたいサッシは付くってもんですが、
まさに想像通りの、いかにもなハリウッド的娯楽映画であります。
「ハリウッド的」という言い方は、
時として否定的なニュアンスで使われたりもしますが、
ここではむしろ肯定的なニュアンスだと思っていただきたい。
CGや奇抜なプロット、役者の個性などに頼り過ぎ、
映画としてのバランスを崩してしまっている作品が多い昨今、
特に破綻もなく、安心して最後まで見られる作品って、
実はそんなに多くないような気がします。
「シンデレラマン」はそんな数少ない映画の一つ。
(しいて言えば、レネー・ゼルウィガーが、
いまひとつハマってないような気がしました…)
| 主なボクシング映画 |
| ロッキー('76) |
| レイジング・ブル('80) |
| ALI アリ('01) |
| ミリオン・ダラー・ベイビー('04) |
■職人的
ときは世界大恐慌時代、貧困のどん底にあり、家族離散の危機に直面していた
ラッセル・クロウ演じる元ボクサー、ジム・ブラドックは、
家族のため、巡ってきたボクサー復活のチャンスに挑む。
年令やブランクをものともせず、勝ち上がっていく過程で、
ブラドックが次第に貧しい人々の希望となっていく様を、
ストーリーテリングの名手ロン・ハワードが、 職人的な実直さで丁寧に描いていきます。
物語自体、特に斬新なものではないし、語り口もいたってオーソドックス。
ただ、レンガ職人がレンガを一つ一つ積み上げるように、
物語を丹念に積み上げていく手法は、好感が持てるし、
職人技ならではのキメの細かさや温もりを感じさせてくれる。
意外に試合のシーンが長い気がしたが、
ダレることがなかったのは、撮り方がうまいせいでしょう。
たまにはこういうオーソドックスな映画もいい。
■ポール・ジアマッティ!
ラッセル・クロウは勿論素晴らしいのだけど、
マネージャー役の俳優がいい味出してる。
この愛嬌ある顔、どこかで見覚えあるなあと思っていたら、
「サイドウェイ」の主役の人だったんですね。
ポール・ジアマッティ。またひとり僕の名優リストに名前が加わりました。
今回の演技は間違いなくアカデミー助演男優賞クラスだと思います。
すでに放送映画批評家協会賞で助演男優賞を獲得しているほか、
16日に発表されたゴールデングローブ賞では
惜しくも受賞は逃したものの、堂々のノミネート。
つまり実力は折り紙付きってわけですね。
今後とも目が離せない俳優さんです。
| 主なポール・ジアマッティ出演作 |
| サイドウェイ('04) |
| アメリカン・スプレンダー('03) |
| PLANET OF THE APES 猿の惑星('01) |
| プライベート・ライアン('98) |
| トゥルーマン・ショー('98) |
■働ける歓び
この映画の舞台である世界恐慌時のアメリカでは
失業率が一時25%にも達したそうです。
てことは4人にひとりが失業者。
麻雀をすれば誰か1人は無職だったわけですね。
しかし、上には上があるもので、
2004年の統計によると(ってことはごく最近の話)、
マケドニアの失業率はなんと37.2%だそうで。
そう考えると、つくづく自分は恵まれた環境にあるなぁ。
仕事があって、お金がもらえて、曲がりなりにも生活をしていける。
毎晩、明日の食べ物を心配する必要もないんだから。
| 失業率 | |
| マケドニア(2004年) | 37.2% |
| アメリカ(世界恐慌時) | 一時25%超 |
| アメリカ(05年12月) | 4.9% |
| 日本(05年11月) | 4.6% |
「街の灯」(1931) [映画の観方]

<原題>City Lights
<監督>チャールズ・チャップリン
<出演>チャールズ・チャップリン、ヴァージニア・チェリル
-------------------------------------------------------------------------
中学の頃、友人とリバイバル上映していた「街の灯」を観に行き、
思いきり笑い転げた記憶がある。
当時でさえ、既に半世紀以上経過した作品であったが、
それが時空を超え、しかも異国の少年を笑い転げさせていたんだから、
考えたら凄いことですよね。
それだけチャップリンの映画が普遍性を持っているということでしょうが、
なかでも、この「街の灯」はダントツの傑作。
チャップリンも相当気合いが入っていたものと思われます。
というのも、この映画が製作された当時は、トーキーが台頭してきており、
無声映画は時代遅れになりつつあった。
そんな中、時代の波に逆らうかのように、あえて無声映画にこだわったチャップリン。
そこには、パントマイム芸人チャップリンの意地とプライドが見える。
すべてをこの映画にかける。そんな意気込みすら感じられます。
チャップリンを語る上で、“笑い”とともに欠かせないのが、“ペーソス”。
つまり、笑えて、泣けるのが、チャップリンの映画。
この映画も両者が高い水準で同居している。
まさに集大成。
ラストは映画史上最も切ないラストだ!(…と言い切ってしまいたい。)
「審判」(1963) [映画の観方]

<監督>オ-ソン・ウェルズ
<出演>アンソニ-・パ-キンス、ジャンヌ・モロ-、オ-ソン・ウェルズ
-------------------------------------------------------------------------
■モノクロ映画
「8 1/2」「博士の異常な愛情」「イレイザーヘッド」「街の灯」…
僕の好きな映画にはなぜかモノクロの映画が多い。
そもそも映画というのは光と影の芸術で、
モノクロというのは、光と影のアンサンブルを最も効果的に見せてくれる。(モノクロの意義はその一点に集約されているといってもいい。)
だからよくできたモノクロ映画というのは、カラー映画にはない独特の美しさがある。
オーソン・ウェルズといえば、映画のランキングなどでは必ずといっていいほど上位に入る「市民ケーン」(最も権威ある映画団体の一つAFI(アメリカン・フィルム・インスティチュート)が1998年、映画誕生100周年を記念して選定したランキングで1位に選ばれる)が有名だが、個人的にはこの「審判」の方が好き。
「市民ケーン」は1941年の監督デビュー作(このときなんとウェルズ26歳!)だが、「審判」はその22年後だから、当然テクニック的にも洗練されてきているだろうし、映画監督としてもまさに脂の乗っている時期だろう。この難しい原作の映像化への挑戦に、彼の自信が見てとれる。
彼を評して“天才”とよくいうが、そんな彼の天才ぶりが存分に発揮されているのがこの作品だと思う。スキのない、完全にコントロールされた映像は、どこを切り取ってもポスターになりそうなくらい美しく、極端な話、音を消して映像だけ見ていても楽しめる。フランス、イタリア、西ドイツ製作という点から見ても、ハリウッド的な文脈から離れ、より自由度の高い芸術性を追求したものであることが伺える。
■不安感の演出
原作はカフカの不条理サスペンス。ある朝、部屋に突然刑事が入ってきて、罪状もよく分からないまま不当な逮捕を言い渡されるところから物語は始まり、まるで夢でも見ているかのような不条理な世界が次々に展開していく。
冒頭から見てみると、まずいきなりクレジットが流れる。古い映画などではたまに見るが、実はこれにもちゃんとした理由があることが最後に分かる。エンディングにはクレジットはなく、代わりにキャストを紹介するウェルズのナレーションで締めているのだ。
クレジットのあとは、クラシカルでもの哀しいテーマをバックに、紙芝居によってある寓話を説明しているのだが、これがアクセントとして利いている(紙芝居は最後にも登場)。この寓話もまた不条理であり、これから始まる物語を暗示している。
 次に徐々にピントが合いながら、寝ている主人公の顔が映し出されるのだが、このとき顔の向きは図のようにあごが左上を向くような格好で、緊張感があり、なにやら普通じゃない感じを漂わせている。
次に徐々にピントが合いながら、寝ている主人公の顔が映し出されるのだが、このとき顔の向きは図のようにあごが左上を向くような格好で、緊張感があり、なにやら普通じゃない感じを漂わせている。
起き上がる主人公の背後にカメラが回り込むと、真っ黒な影と化したその後ろ姿越しに、向いの白い壁の前に浮かぶ見知らぬ男の姿。光と影のコントラストが見事な象徴的なシーン。
その後、部屋の中で約4分間の長回しが続くのだが、カメラは人物の動きに合わせて、前後左右に動くだけでなく、時に下からのアングルになるなど、狭い空間(実際に低い天井!)で限定される動きの中で、決して単調にならず、飽きない画面。
またこのシーンでは、よく耳を澄まさなければ聞き逃してしまうほど微かに、時計の音らしきカチカチというクリック音が聞こえるのだが、これも不安感を煽るサブリミナル効果を狙ったものだろう。
こうしてみると、このオープニングにこの映画全体を貫く特徴的な点がすべてが見られる。
ポイントは以下の4つ。
①空間を感じさせるカメラワーク
冒頭の長回しに象徴されるように、スムーズで自由自在なカメラワークには本当に惚れ惚れしてしまう。空間を感じさせるカメラワークは、特に屋外、あるいはオフィスや法廷のような広い空間を効果的に映し出す。
②ダイナミックな構図
迫力ある下からのアングルや、遠近法によって奥行きを感じさせる構図、それにカメラの動きが有機的にからみ合い、画面に強力なダイナミズムを生みだしている。
主人公が初めて弁護士(ウェルズ)に会う場面では、遠近法の強調によりウェルズを実際より大男に見せ、巨大な壁(障壁)であることを示唆している。
③光と影のアンサンブル
ウェルズはまるで光の魔術師とでも呼びたくなるほど、光を完璧に操っているようだ。揺れるランプの灯で見え隠れする顔。稲光りでの同様の効果。格子状の隙間から差し込む光。人物の影。半分だけ浮かび上がる顔(「ウィズ・ザ・ビートルズ」のジャケットを思わすような)、柱や手すり、はり巡らされた鉄骨などの映し出す幾何学的な影・・・それら光と影が織り成す一大パフォーマンスが画面に深みと複雑な表情を与える。
主人公が錯綜する光と影の中を走り抜けるシーンは幻想的で、バックに流れるアップテンポのフリージャズの焦燥感、追い掛けてくる子供の笑い声の不気味さも手伝って、最も印象的なシーンだ。
④音楽の効果
メインテーマは出口のない結末を暗示しているかのような、もの哀しさに満ちている。また不安を誘うようなフリージャズやサブリミナル的に訴えるクリック音(冒頭の時計の音の他、弁護士の屋敷で、主人公が別の被告人に秘密を打ち明けられる場面では、テンポが徐々に速くなっていくクリック音が聞ける)などが効果的に使用される。
以上4つのポイントはすべて不条理な出来事に対する不安感の演出という点に集約される。
思えば、彼を一躍有名にしたのは、H.G.ウェルズ原作「宇宙戦争」(現在スピルバーグ、トム・クルーズのコンビで映画化が話題の)のラジオドラマだった。当時、本当に宇宙人が襲ってきたと勘違いした人々が続出し、全米がパニックになったのは有名な話。このことは彼の演出がリアルであったことの証で、人々の不安感を操作するという点では、のちの「市民ケーン」「ストレンジャー」「黒い罠」などへと続いていくサスペンス的手法が、既に高い完成度にあったことを物語っている。
「審判」もそうした一連の作品の流れにあり、彼の得意とするサスペンス的演出が冴えわたる。と同時に、いやそれ以上に、彼の芸術性の高さだったり、モノクロの美しさを感じさせてくれる映画だ。
「博士の異常な愛情/または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか」(1964) [映画の観方]
<原題>Dr.Strange Love:Or How I Learned To Stop Warrying And Love The Bomb
<監督>スタンリー・キューブリック
<出演>ピーター・セラーズ
-------------------------------------------------------------------------
■これもタイトルがいいですね(「8 1/2」もそうですけど、タイトルは重要です!)。なんとも長いタイトルですが、遊び心があります。一目でコメディだと分かるし。邦題も原題の意図を忠実に汲んでますね。
それにしてもこの長いタイトル、製作サイドは嫌がったんじゃないでしょうか。観客が覚えづらいとかなんとか言って。そういえば、ビートルズにも「Everybody's Got Something To Hide Except Me And My Monkey」という長いタイトルの曲がありました。ジョンの曲ですが、彼らしいユーモアを感じます。
■ピーター・セラーズ、1人3役
キューブリックといえば、「2001年宇宙の旅」や「時計じかけのオレンジ」の印象が強いですが、僕はこの「博士の異常な愛情」と「ロリータ」が好きです。そしてそのどちらにもピーター・セラーズが出てるんですね。
この人もかなり好きな役者さんです。いわゆる正当派ではなくコメディアンなんですが、ディフォルメされた個性的なキャラクターを演じ分けさせたらこの人は一番じゃないでしょうか。
「ピンク・パンサー」のクルーゾー警部役が有名ですが、「チャンス」での庭師役など、ほんとに印象に残る、そして笑える役が多いです。
この「博士の異常な愛情」はそんなピーター・セラーズが1人3役を演じており、まさに彼の真骨頂と言えるでしょう。実は白状すると、初めてみたときは1人3役だと気付きませんでした。後でその事実を知って衝撃を受けたのを覚えています。
■リアルな戦闘シーン
映画は冷戦下の核の脅威、戦争の愚かさをブラックに描いたコメディで、みどころは何と言ってもピーター・セラーズのなりきりぶりなんだけど、実はあまり語られてませんが、この映画の凄いところはリアルな戦闘シーンの描写にあると思います。
狂った司令官によって外部と隔絶された部隊と、大統領の命で彼を捕らえようとする部隊が市街戦を繰り広げるんですが、このシーン、まるでニュース映像を見ているかのような迫力。基本的に、カメラは常に後方からのアングルで撮られています。金網越しであったり、銃を連射する兵士の肩ごしであったり。つまり、実際にその場にいる者(戦場カメラマン、もしくは兵士)の目線で描かれているわけです。
実際に銃撃戦が行われている中で、正面から撮るということは、カメラが撃ち合っている両者の間に位置することになるから、リアルさとはかけ離れたものとなるでしょう。ここでは正面からに見えるショットでも、手前に木の影などが映りこんでおり、目線の主は常に遠く物影に隠れていることが分かります。
そしてまた手持ちカメラ(だろうと思われる)によるブレや不安定な目線の動きなども、その場にいる者の恐怖や緊張感、あるいは予測不能な事態に対して即興で対象に目線を動かす様子を見事に表現しています。
このリアルな戦闘シーンの描写により、画面に一段と緊張感が生まれ、それが緊張と緩和の落差を大きくしているんですね。これにより、エンディングでのカタルシス効果はより強くなっています。
■「プライベート・ライアン」「ブラックホーク・ダウン」
 |
 |
スピルバーグの凄いところは、こうした非日常的な映像をいとも簡単に(実際はそんなことはないでしょうが)作れるところだと思います。「未知との遭遇」における宇宙船、「E.T」における宇宙人、「ジュラシック・パーク」における恐竜など。
冒頭数十分にも及ぶ執拗なまでの戦闘シーンは、カメラの揺れによる気分の悪さを、戦闘シーンの生々しい描写による気分の悪さに置き換えようとする意図もあったのではないでしょうか。
唯一残念なのは、トム・ハンクスの存在。別にトム・ハンクスが悪いわけじゃないけど、彼が画面に出ているだけで、ああ、これは映画なんだ、とどこか醒めて見てしまいました。
個人的には同じ戦争ものとしては、リドリー・スコット監督「ブラックホーク・ダウン」の方に軍配が上がります。こちらはコマーシャルかと思うくらい綺麗な映像で、およそリアルとはかけ離れた映像ですが、映画的な迫力という意味では負けてないような気がします。反ドキュメンタリーで、戦闘シーンなども忠実に描かれていたようですが、撮り方がうまいから全く飽きさせない。特に中盤以降は引き込まれました。
・The Authorized Stanley Kubrick Web Site
「8 1/2」(1963) [映画の観方]
<監督>フェデリコ・フェリーニ
<出演>マルチェロ・マストロヤンニ、アヌーク・エーメ
-------------------------------------------------------------------------
 ■まずタイトルがいいです。8でもなく、9でもなく8 1/2というところがお洒落。ただこれを日本語で発音してしまうと「ハチトニブンノイチ」でしょ。「ハチト」の「ト」がなんだか間抜けですよね。あるいは「ハッカニブンノイチ」と読むのかな?…どっちにしろ間抜け。あと「1/2」はやっぱり小さく書きたいところですが、パソコンだと通常「8」と同じ大きさで表記されてしまう。これだと「2分の81」にも見えるし、分かりづらい。8と1の間を半角を空けることによって暗黙の了解として、「8と2分の1」と読んでるけど、あまりスマートじゃない。その辺が残念と言えば残念。ちなみに"8
1/2"という数字はフェリーニがそれまでに撮った映画の数(長編8本+短編1本)を表しているそうですが、ちゃんと内容にもかかっているんですね。
■まずタイトルがいいです。8でもなく、9でもなく8 1/2というところがお洒落。ただこれを日本語で発音してしまうと「ハチトニブンノイチ」でしょ。「ハチト」の「ト」がなんだか間抜けですよね。あるいは「ハッカニブンノイチ」と読むのかな?…どっちにしろ間抜け。あと「1/2」はやっぱり小さく書きたいところですが、パソコンだと通常「8」と同じ大きさで表記されてしまう。これだと「2分の81」にも見えるし、分かりづらい。8と1の間を半角を空けることによって暗黙の了解として、「8と2分の1」と読んでるけど、あまりスマートじゃない。その辺が残念と言えば残念。ちなみに"8
1/2"という数字はフェリーニがそれまでに撮った映画の数(長編8本+短編1本)を表しているそうですが、ちゃんと内容にもかかっているんですね。
■内容は、フェリーニ自身の投影ともとれる映画監督のグイドが、映画製作に行き詰まり、保養地に温泉治療に出かけるんですが、売り込みに必死な女優や、進行状況を気にする製作者、記者などに追い回され、治療に専念できない。さらに妻を呼び寄せるも浮気がばれて険悪になり、映画製作は一向に進まない。そんなグイドの苦悩を現実と虚構(夢、妄想、幼少期の記憶、劇中劇)を織りまぜながら描いていくというものです。
特に妄想のシーンは秀逸で、特殊効果や特撮などで、シュールな世界をうまく映像化してます。
たとえば冒頭、渋滞の車から抜け出し、空を昇るグイド。しかし彼の足にはヒモが括りつけられていて、地上へ引っ張り下ろされる。このシーンは遅々として進まない映画製作から逃れようとするが、結局逃れられないというストーリーを象徴するシーンで、導入部としては見事な導入部です。
また、彼とこれまでに関わった女性たちが仲良く共存するハーレムの妄想シーンは華やかさと力強さに溢れていて、この映画のハイライトの一つでしょう。音楽の使い方もうまいです。
そしてラスト、「人生は祭りだ、ともに生きよう」というグイドの"答え"を象徴するラストのダンスシーンは圧巻で、映画的な着地を見事に決めてくれます。こうした映画のカタルシス作用としての"祭り"は他のフェリーニ作品(「カリビアの夜」、「オーケストラ・リハーサル」など)にもしばしば見られます。
■ゴッホの「ひまわり」、ピカソの「ゲルニカ」、岡本太郎の「太陽の塔」など有無を言わせぬ圧倒的な力を持った作品というのがあります。「8 1/2」もまさにそんな作品のひとつだと思います。
一見、難解な映画に思われがちですが、僕は決してそうではないと思うんですね。かといって「道」のような分かりやすいストーリーがあるわけではないけど。
デヴィッド・リンチをはじめ、多くの映画監督に人気があるのは、映画監督そのものを題材としていることもあるんでしょうが、やはり単純に"センスがいい"というのが一番の理由だと思います。
脚本、構成、色彩感覚、構図、カメラワーク、音楽、演技など、どれをとっても素晴らしく、まさに総合芸術として完成度の高い作品ではないでしょうか。個人的には絵画的な構図と流れるようなカメラワークに特にセンスを感じます。
だから観るときも、本当は絵画やオブジェといった芸術作品を鑑賞するように見たほうがいいと思います。ただ2時間20分もそのような見方で観るのはしんどいかも知れませんね。そういう意味ではある程度の忍耐力を要求される映画です。
途中で飽きてしまってもそれはそれで仕方ないと思います。実は僕も1回目は退屈で半分寝てしまいましたから。けど、我慢して最後まで見れば(ま、我慢する必要はないですが…)きっと何かしら発見があると思います。
何気ない会話のシーンにドキッとするようなリアルな描写が見てとれたり、何気ないシーンにこそ美しいカットが潜んでいたりするので、一瞬たりとも油断が出来ません。
■演技に関して言えば、マルチェロ・マストロヤンニはとにかく絵になりますね。サングラスを指で下げるシーン、おどけたステップを踏んでみせるシーン…、一つ一つの動作が逐一絵になります。ダンディな中にも茶目っ気のあるところがいいですね。
アヌーク・エーメも素晴らしく、マルチェロ・マストロヤンニとの夫婦のやりとりを描いたシーンなどは、二人の微妙な関係をうまく表現していると思います。
それにしても未だにDVD化されないのはなぜなんでしょうか?